部下のモチベーションが上がらない…
チームのパフォーマンスが停滞している…
あなたの職場は、こんな悩みを抱えていませんか?
「もしアドラーが上司だったら」は、アドラー心理学をビジネスの現場で実践し、チームを劇的に変革するための実践的ガイドブックです。
広告代理店を舞台にしたストーリー形式で、心理学の専門知識がなくても、楽しみながら具体的な職場改善のヒントを得ることができます。
本書は、「嫌われる勇気」で注目を集めたアドラー心理学を、あなたのチームの成長に直結させる実践的手引書です。
広告代理店を舞台にしたストーリーを読み進めながら、「勇気づけ」「共同体感覚」「課題の分離」といった、アドラー心理学の重要概念を、無理なく理解できます。
本記事では、本書の要約と、あなたのチームを劇的に変えるヒントをお届けします。
この本が描く、変革のストーリー:北野課長と南の成長物語
「もしアドラーが上司だったら」は、広告代理店「大日広告」の営業二課を舞台に、一人の課長がアドラー心理学を実践し、部下と共に成長していく物語です。
悩める上司の出発点:トップセールスから管理職へ
かつてのトップセールスであった北野課長は、課長に昇進した今、部下育成に大きな壁に直面していました。
特に、新人の南は、モチベーションが低く、指示待ち状態で、なかなか成果を上げられません。
当初、北野課長は自身のセールス経験から、厳しい指導で部下を律しようとしました。
「俺の若い頃は…」と、かつての自分のやり方を押し付け、南にもガツガツと行動するよう求めました。
しかし、南は萎縮するばかりで、状況は一向に改善されませんでした。
アドラー心理学との出会い:マネジメントの転換点
そんな中、北野課長は「アドラー心理学」に出会います。
最初は「本当に効果があるのか?」と半信半疑でしたが、学んでいくうちに、自身のマネジメントスタイルを根本から見直すきっかけとなりました。
特に、「勇気づけ」「共同体感覚」「課題の分離」という3つの概念は、北野課長のマネジメントに革新をもたらします。
アドラー心理学の3つの核心的概念:チームを成長させる具体的アプローチ
本書のストーリーを通して、アドラー心理学の重要な概念が、どのように実践されるのかを具体的に理解することができます。
ここでは、その中でも特に重要な、3つの概念について解説します。
1. 共同体感覚:チームの力を引き出す
アドラー心理学の最も重要な概念の一つが「共同体感覚」です。
これは、自分が組織や社会の一員であるという意識、そして、他者や社会に貢献したいという気持ちを意味します。
北野課長は、一方的に指示を出すのではなく、部下と共に目標を設定し、お互いをサポートし合う風土を作ることに注力しました。
個人目標ではなく、チーム全体の目標に向かって進むことで、チームの一体感とパフォーマンスは劇的に向上しました。
実践例:
- チーム全員で目標設定会議を行い、一人ひとりの役割と貢献を明確にする。
- 週に一度、チームミーティングを開催し、進捗状況の共有と、お互いの仕事をサポートし合える体制を構築する。
- チームの目標達成に対して、全員で喜びを分かち合う文化を作る。
これらのような取り組みを通じて、北野課長は営業二課に「共同体感覚」を醸成し、チーム全体のパフォーマンスを向上させていきました。
2. 勇気づけ:褒めることを超えた成長支援
従来のマネジメントでは「褒める」ことが重視されてきましたが、アドラー心理学では、安易な褒め言葉が逆効果になる可能性を指摘しています。
なぜなら、「褒められる」ことが目的になってしまうと、人は褒められるために行動するようになり、自発的な行動が減ってしまうからです。
北野課長は、南の小さな成功も積極的に認め、「君ならできる」と励まします。
結果、南は自信をつけ、自発的に考え、行動するようになりました。
単に結果を褒めるのではなく、努力の過程や可能性を認めることで、南の内面的成長を促したのです。
「勇気づけ」の具体例
NG例:
- 「すごいね!」(結果だけを褒める、抽象的)
OK例:
- 「この資料、すごくわかりやすいね!特に、図表の見せ方が素晴らしいよ。努力したんだね。」(具体的な行動とプロセスを認め、勇気づける)
- 「君の意見はいつも参考になるよ。ありがとう。」(存在そのものを認め、感謝を伝える)
- 「今回は残念だったけど、次はきっとうまくいくよ。一緒に頑張ろう。」(失敗を責めず、未来への希望を示す)
3. 課題の分離:適切な距離感で、部下の自立を促す
アドラー心理学の「課題の分離」は、自分の課題と他者の課題を明確に区別することを意味します。
北野課長は、南が重要なプレゼンで失敗した際、以前であれば厳しく叱責し、自分が代わりにやってしまっていたかもしれません。 しかし、アドラー心理学を学んだ後は、南自身が失敗から学ぶことをサポートすることに徹しました。
具体的には、南に反省点を考えさせ、改善策を一緒に検討。 過度な干渉を避け、南が自ら考え、行動することを促しました。
実践のポイント:
- 部下の失敗に対して、過度に責任を感じたり、叱責したりするのではなく、「これは彼の課題だ」と認識する。
- 部下が自分で問題を解決できるよう、サポートに徹する。(例:質問にはすぐに答えず、まずは部下自身に考えさせる)
- 「いつでも相談に乗るよ」という安心感を与えつつ、部下の自立を促す。
この本で得られる最大の学び:具体的な行動指針
本書「もしアドラーが上司だったら」を読むことで、あなたは以下の具体的な行動指針を得ることができます。
- 部下のモチベーションを引き出す「勇気づけ」のスキル
- 具体的な行動、プロセス、努力を認める言葉がけを実践する。
- 部下の存在そのものを認め、感謝の気持ちを伝える。
- チームの一体感を高める「共同体感覚」の育て方
- チーム全員で目標設定を行い、役割分担を明確にする。
- 定期的なミーティングで、進捗状況を共有し、サポートし合える体制を構築する。
- ストレスの少ない人間関係を実現する「課題の分離」の考え方
- 部下の課題に過度に介入せず、彼らの自立を促す。
- 「これは自分の課題か、それとも部下の課題か」を常に意識する。
アドラー心理学を実践するために:小さな一歩から始めよう
アドラー心理学の真の学びは、完璧を目指すことではありません。 日々の小さな実践の積み重ねこそが、あなたとチームの成長につながります。
例えば、今日からできることとして、部下の話を「聴く」ことを意識してみてはいかがでしょうか。 「聴く」ことは「勇気づけ」の第一歩です。
まとめ
「もしアドラーが上司だったら」は、単なる理論書ではなく、現実の職場で活用できる具体的な行動変容のガイドブックです。
あなたのリーダーシップと職場環境を、根本から変える可能性を秘めた一冊と言えるでしょう。

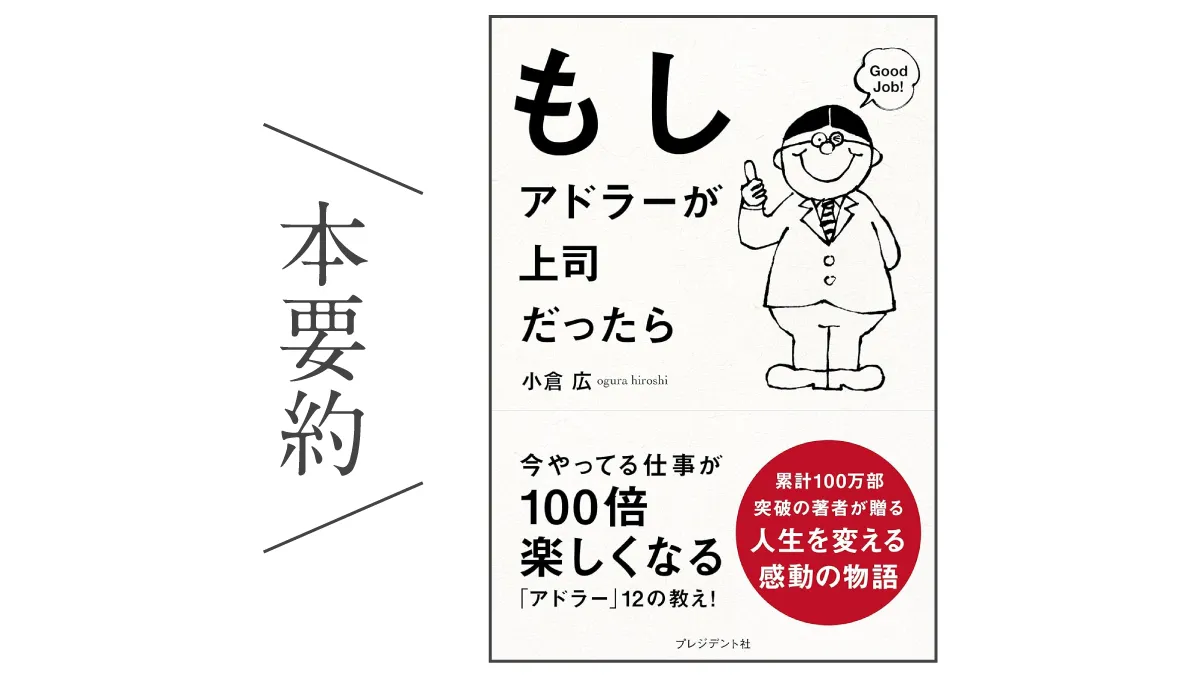
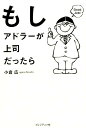
コメント