「似た者親子」なんて言葉をよく耳にしますよね。
遺伝的な要素ももちろん大きいけれど、実は子供は無意識のうちに親の真似をしているんです。
それには深い理由があるってご存知でしたか?
今回は、心理学者のアルフレッド・アドラーの名言を手がかりに、親子が似てくる不思議なメカニズムを、ちゃんこ先生と一緒に解き明かしていきましょう。
親子が似るのは遺伝だけじゃない
レイコ:今日はちょっと気になっていたことがあって来たんです。
私、母に顔も性格もそっくりってよく言われるんですけど、なんで親子ってこんなに似るんでしょう?
遺伝だけじゃ説明できないような気もして…。
ちゃんこ先生:確かに、遺伝で顔のつくりや体質は似るものです。
しかし、それだけでは説明がつかないほど、話し方や仕草までそっくりな親子も多いですよね。
心理学者のアルフレッド・アドラーは、こんな名言を残しています。
身振りや話し方が親に似るのには理由がある。
子供は親を真似ることで親の権力を手に入れようとし、結果として本当に似てくるのだ。
レイコ:ええ!! 親の権力を手に入れるため!?
なんだかすごい話ですね…。
ちゃんこ先生:はい。では、ゆっくり解説していきますね。
子供は、無意識のうちに家庭という小さな社会の中で、自分の居場所を確立しようとしているのです。
そこで有効な手段となるのが、「親を真似ること」なんです。
子供は親を真似て力を得ようとする
レイコ:親を真似ると「力」が手に入るんですか?具体的にはどういうことなんでしょう?
ちゃんこ先生:子供にとって、親はとても大きな存在です。
特に、力を持っていると感じる親を真似ることで、「自分もその力の一部を手に入れたい!」と無意識に思うのです。
親との同盟をアピール
ちゃんこ先生:まず一つ目の理由は、親との同盟関係を他の家族にアピールするためです。
例えば、お父さんと仲良しな子供は、お父さんの口癖や仕草を真似ることで、「私はお父さんの味方だよ!」と、お母さんや兄弟にアピールするのです。
そうすることで、家庭内での自分の立場を強くしようとするんですね。
レイコ:なるほど、確かに!「お父さんにそっくりね!」なんて言われたら、お父さんも嬉しくなって、ますます自分のことを守ってくれそうですよね。
ちゃんこ先生:そうそう。子供は周りの反応を見ながら、無意識に戦略を立てているんです。
嫌いな親にも似てしまう?権力の象徴を真似る子供の心理
ちゃんこ先生:しかし、子供は好きな親だけを真似るわけじゃないんですよ。
時には、厳しくて怖い、嫌いな親に似てしまうこともあるんです。
レイコ:ええ!?嫌いな親なのに?それは、どうしてなんでしょう?
ちゃんこ先生:それは、その嫌いな親が子供にとって「権力の象徴」に見えるからです。
家庭の中で力を持っている親を真似することで自分もその力を手に入れようとするんです。
厳しい言葉遣いや威圧的な態度を真似てしまうのは、そういった無意識の心理が働いているからかもしれませんね。
レイコ:確かに、厳しいお父さんって、家庭の中で一番強かったりしますよね…。
でも、真似しているうちに、本当に嫌な性格まで似てきたら、それはそれで辛いですよね…。
ちゃんこ先生:そうですね。でも、子供は親の全てをコピーするわけではありません。
良いところも悪いところも、部分的に真似していく中で、自分なりの個性も育っていくんですよ。
「似る」ことで安心感を得る
ちゃんこ先生:そして、もう一つの理由は、「似る」ことで安心感を得ようとするからです。
特に自分に自信がなかったり、不安を感じやすい子供は、頼りになる親に似ることで心の安定を図ろうとします。
レイコ:その気持ちわかる気がします。
私も、母と似てるって言われると、なんだか嬉しいし、安心するんですよね。
ちゃんこ先生:そうでしょう?子供にとって、親は最も身近なモデルです。
真似をして、似ていくことで「自分も親のように、強く優しくなれる」という希望を持てるのかもしれませんね。
具体例:日常生活の中の「親子そっくり」エピソード – 無意識の模倣と学習
ちゃんこ先生:では、ここで日常生活の中にある「親子そっくり」エピソードについて、より詳しく見ていきましょう。
子どもたちは、意識せずとも親の行動や特徴を自然に取り入れていきます。
言葉遣いと表現方法
親がよく使う言葉や表現は、子どもの言語形成に大きな影響を与えます。
例えば、「まったくもう!」「しょうがないわねぇ」といった親の口癖は、まるでDNAの一部であるかのように子どもに受け継がれていきます。
さらに興味深いのは、イントネーションや言葉の抑揚まで似てくることです。
時には、祖父母の代から続く独特の言い回しが、何世代にもわたって受け継がれることもあります。
身体的な特徴と癖
体の使い方や動作の特徴も、驚くほど親子で似通ってきます。
歩き方はその典型例です。
足の運び方、腕の振り方、そして立ち方まで、まるでコピーしたかのように親子で一致することがあります。
また、食事の際の箸の持ち方や、物を手に取る仕草なども自然と似てきます。
面白いことに、猫背や肩の力の入れ方といった、必ずしも良いとは言えない姿勢の癖まで継承されてしまうことがあります。
趣味嗜好と生活習慣
親子の共有時間が長いことで、趣味や好みも自然と重なってきます。
これは単なる模倣を超えて、深い心の絆(感情的な絆)を形成する重要な要素となります。
- 音楽の好みは特に影響を受けやすく、親が聴いていた音楽は子どもの原風景として心に刻まれます
- 食の好みも強く影響を受け、親が好む味付けや料理が「心の定食」として定着します
- 休日の過ごし方や趣味の選択にも、親の影響が色濃く反映されます
レイコ:ありますね、そういうこと!
私も、母の好きな昭和歌謡、いつの間にか一緒に口ずさむようになっちゃいました。今では娘と三世代で同じ曲を楽しんでいます。
ちゃんこ先生:素敵なエピソードですね。
このような世代を超えた共通体験は、家族の絆をより深めてくれます。
こういった日常の何気ない瞬間が、実は子どもの人格形成や価値観の醸成に大きな影響を与えているのです。
ただし、これは必ずしも意図的な教育や躾の結果ではなく、むしろ日々の自然な交流や共有体験を通じて築かれていく、という点が興味深いところです。
よくある質問
- Q親と性格が全く似ていない場合もありますが。
- A
性格は遺伝だけでなく、育った環境や経験によっても大きく影響を受けます。
また、あえて親とは違う道を選ぼうとする場合や、「反面教師」として、親とは異なる性格を形成することもあります。
- Q仲の悪い親子でも、似てしまうことはありますか?
- A
はい、あります。先述した通り、子供は、好き嫌いに関わらず、力を持っていると感じる親を真似る傾向があります。
そのため、仲が悪くても、親の持つ権力を手に入れたいという無意識の欲求から、似てしまうことがあるのです。
- Q親の良いところだけを真似ることはできますか?
- A
完全に親の良いところだけを真似ることは難しいですが、意識することで、ある程度はコントロールできるかもしれません。
親の良いところを尊敬し、積極的に見習うようにすることで、良い影響を受けることができるでしょう。
- Q親に似たくない場合は、どうすればいいですか?
- A
まずは、なぜ親に似たくないのか、その理由を考えてみましょう。
そして、自分が理想とする人物像を明確にし、その人に近づくためにはどうすれば良いかを考えてみましょう。
大切なのは、親を否定するのではなく、自分自身がどうありたいかを考えることです。
まとめ
レイコ:ちゃんこ先生、今日は本当にありがとうございました!
親子が似るのには、遺伝だけじゃなくて、子供の無意識な戦略が関係していたなんて、目から鱗でした。アドラー心理学、もっと勉強してみたくなりました!
ちゃんこ先生:それは良かったです。アドラー心理学は、知れば知るほど奥が深い学問です。
ぜひ、レイコさんも、自分自身や周りの人との関係をより良くするために、学んでみてくださいね。
そして、子供は親を映す鏡です。子供が健やかに成長できるよう、私たち大人も、子供にとって良い手本となるよう、日々努力していきたいものですね。

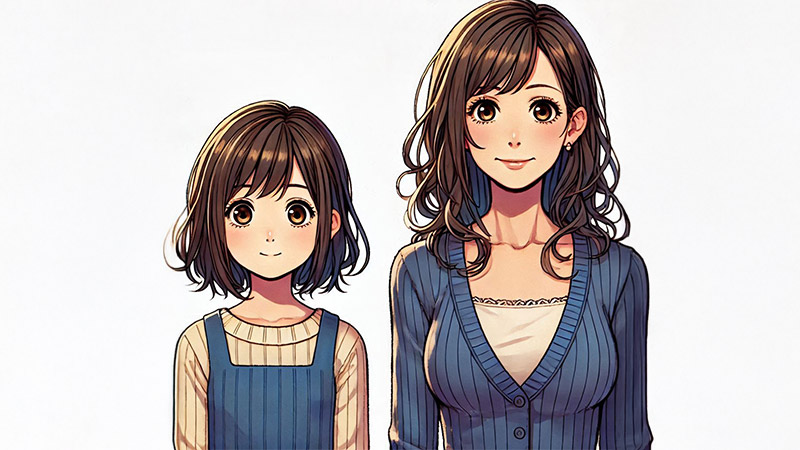
コメント